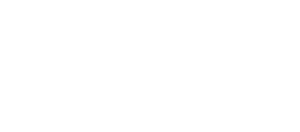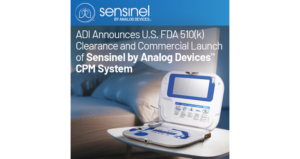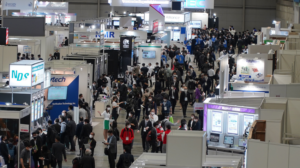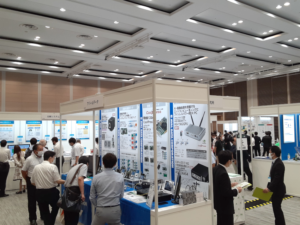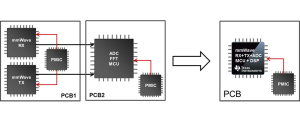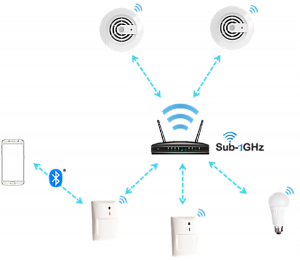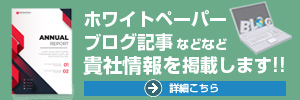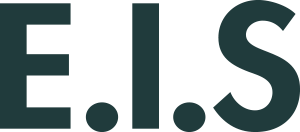横田英史の読書コーナー
宇宙の地政学
倉澤治雄、ちくま新書
2024.8.3 10:56 am
月や火星などをターゲットにした、日米欧や中国、ロシア、インドの宇宙開発競争を、日本テレビの記者出身の科学ジャーナリストが手際よくまとめた書。各国の宇宙開発の歴史やロケット技術、発射場、資源開発、研究者の人脈などについて分かりやすく解説する。先行する米国、猛追する中国といった構図がよく分かる。宇宙関連のニュースが新聞紙上やネットを騒がすことはなくないが、散発的に報道されるのでどうしても全体像が見えなくなる。本書は網羅性に優れるので、宇宙開発の状況をざっくり把握するのに役立つ。宇宙ビジネスに興味のある方にお薦めの書である。
本書は大きく6つの章で構成する。月面探査や基地建設など月をめぐる競争、宇宙における米中摩擦、国家の威信をかけた中国の宇宙開発、米国の宇宙ベンチャー、日本の宇宙開発と宇宙安全保障である。特に、月の裏側の土壌サンプルを持ち帰るなど、活発化する中国の宇宙開発戦略とその技術力に多くのページを割いており読み応えがある。米国を猛追する中国だが、量子衛星通信では先頭を走っているという。このほか米国ベンチャーの動向もなかなか興味深い。
米ソから米中へ、国策から民間へ、国威発揚からビジネスへ、平和利用から軍民一体へ、といった宇宙開発の変化が本書を読むと良いわかる。それにしても、米中が火花を散らす激戦区となっている月と火星関連の話は興味深い。例えば、人間の生存に不可欠な水の存在や、月表面の「レゴリス」と呼ばれる土壌の存在などもあり、月を巡る開発競争は面白い。レゴリスには鉄などの成分が含まれており、3次元プリンティング技術を用いて構造物の建設が可能になるという。
書籍情報
宇宙の地政学
倉澤治雄、ちくま新書、p.272、¥1012

横田 英史 (yokota@et-lab.biz)
1956年大阪生まれ。1980年京都大学工学部電気工学科卒。1982年京都大学工学研究科修了。
川崎重工業技術開発本部でのエンジニア経験を経て、1986年日経マグロウヒル(現日経BP社)に入社。日経エレクトロニクス記者、同副編集長、BizIT(現ITPro)編集長を経て、2001年11月日経コンピュータ編集長に就任。2003年3月発行人を兼務。
2004年11月、日経バイト発行人兼編集長。その後、日経BP社執行役員を経て、 2013年1月、日経BPコンサルティング取締役、2016年日経BPソリューションズ代表取締役に就任。2018年3月退任。
2018年4月から日経BP社に戻り、 日経BP総合研究所 グリーンテックラボ 主席研究員、2018年10月退社。2018年11月ETラボ代表、2019年6月一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)理事、現在に至る。
記者時代の専門分野は、コンピュータ・アーキテクチャ、コンピュータ・ハードウエア、OS、ハードディスク装置、組込み制御、知的財産権、環境問題など。
*本書評の内容は横田個人の意見であり、所属する企業の見解とは関係がありません。
新着記事
-

生成AIのしくみ〜〈流れ〉が画像・音声・動画をつくる〜
2025.1.1 1:19 pm
-

地面師〜他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団〜
2024.12.30 1:18 pm
-

VTuber学
2024.12.28 1:16 pm
-

デジタル脳クライシス〜AI時代をどう生きるか〜
2024.12.15 1:15 pm
-

経営理念が現場の心に火をつける
2024.12.10 1:13 pm
-

破壊なき市場創造の時代〜これからのイノベーションを実現する〜
2024.12.8 1:11 pm
-

〈弱いロボット〉から考える〜人・社会・生きること〜
2024.11.29 12:15 pm
-

コモングッド〜暴走する資本主義社会で倫理を語る〜
2024.11.26 12:11 pm
SOLUTION
REPORT
横田英史の 読書コーナー
お薦めセミナー・イベント情報
ET/IoT Technology Show
Back Number
Pick Up Site
運営

株式会社ピーアンドピービューロゥ
〒102-0074
東京都千代田区九段南4-7-22
メゾン・ド・シャルー3F
TEL. 03-3261-8981
FAX. 03-3261-8983