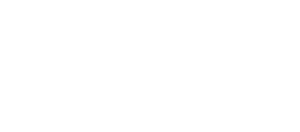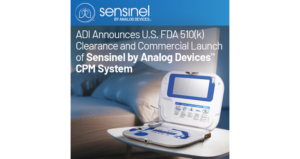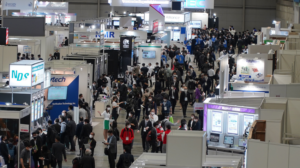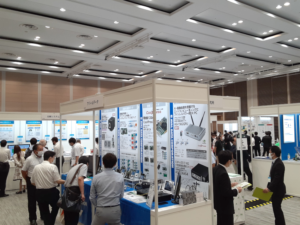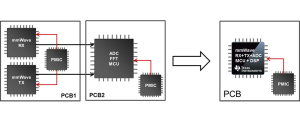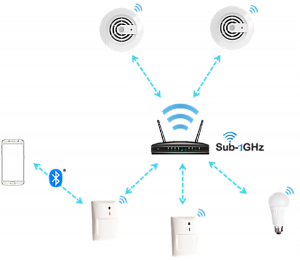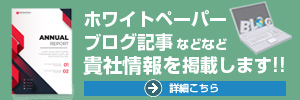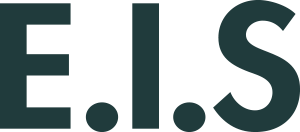横田英史の読書コーナー
ヒューマンエラーは裁けるか 新装版〜安全で公正な文化を築くには〜
シドニー・デッカー、芳賀繁ほか・訳、東京大学出版会
2024.8.31 11:38 am
人間が引き起こすミス(ヒューマンエラー)を裁判や人事的な懲罰などで対処することの問題点を論ずるとともに、どうすればヒューマンエラーから学べる組織を構築できるかを考察した書。医療・航空などの事故当事者から得た具体的な実例を詳細に分析しており役立ち感がある。日本の航空・鉄道・医療事故に関する事例については、分量としては少ないが監訳者の解説で補う。セキュリティを含めヒューマンエラーを報告しやすい組織文化について関心のある方にお薦めの1冊である。
著者が必要性を訴えるのは原書のタイトルになっている「Just Culture(公正な文化)」。大きく2つのポイントがある。起きてしまった事故から最大限の学習をし、それによって安全性を高める対策を講じること。もう一つは、事故の被害者や社会に対して最大限の説明責任を果たすことである。この2つんぼ目的を達成するための挑戦を続ける組織文化を「Just Culture」と呼んでいる。後知恵による失敗追求を厳に戒める。
筆者は、ヒューマンエラーは原因ではなく組織の症状だと訴える。システム内部の深いところにある問題の発露だとする。裁判は民事であっても刑事であってもヒューマンエラーの抑止力として機能しない。例えば防衛的な医療や質の低い医療につながったり、インシデント(事故)の報告が減るだけである。かえってインシデントの発生率を高めてしまう。裁判や解雇、降格、停職などは個人にとっても組織にとっても、安全性向上には何の役に立たない「後ろ向きな責任」でしかない。
本書は2009年に出版された初版の装丁などを変えた「新装版」。原書は第2版、第3版が出版されており、本書の元である第1版(2008年刊)にたいして加筆だけではなく章の構成も変えている。とても有意義な書なので、出版社が新装でお茶を濁し、最新版を反映し「改訂」しなかったのはとても残念である。ちなみに、「ハドソン川の奇跡」と呼ばれた「USエアウェイズ1549便不時着水事故」のチェズレイ・サレンバーガー機長が本書を図書館で借り、事故当日に持っていたことでも知られる。
書籍情報
ヒューマンエラーは裁けるか 新装版〜安全で公正な文化を築くには〜
シドニー・デッカー、芳賀繁ほか・訳、東京大学出版会、p.304、¥3300